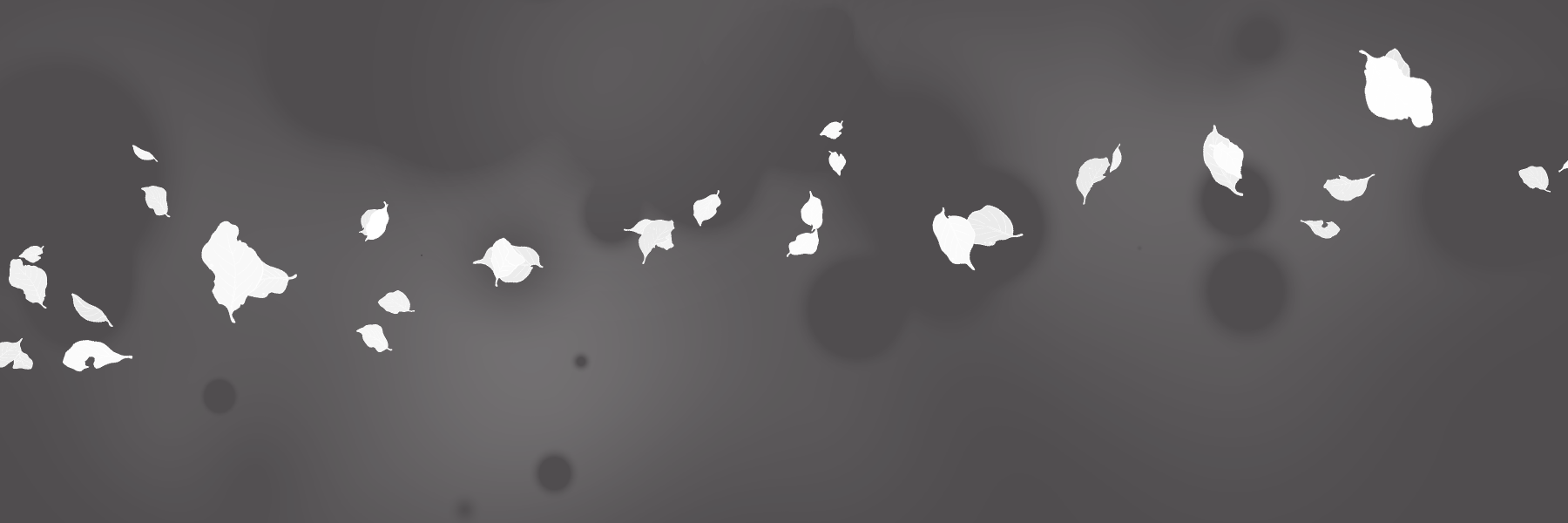セカイ ノ オワリ
その日はいつもと変わらなかった。朝起きて、顔を洗ってご飯を食べて、化粧して会社に行った。
いつも通り、書類を処理して上司に提出。オッケーをもらって、残業もない。苦手なオツボネ様からもちょっとしか嫌味を言われないで済んだ。
「あなたの髪のリボン、青じゃうちの制服と合わないわよ。せめて白に変えて」
だって。
大きなお世話。
でも言われると気にしちゃう。小心者の私。来週はリボンじゃなくてピンに変えよう。トラブルは嫌いだ。
早く終わったのに、誰にも誘われることなく家路についた。私は人付き合いが苦手。良くないと思いつつ、親しい友人以外には自分のことは話さない。
駅について電車に乗る。帰宅ラッシュなので空いてる座席はない。立ったまま、電車の窓から夕日を眺める。
ものすごい赤だ。「空が燃え上がる」 という在り来りな言葉が頭に浮かぶ。
違和感を覚えたのは、二つ目の駅を通り越して、いつも見える神社の大木を見た時。あの木……あんなに小さかったっけ?
そうじゃない。
〝小さくなった〟と言うより〝萎れている〟という感じがする。
何だか胸の奥がザワザワする。夕日はますます色を濃くして、私の周りの空気まで赤に侵食されて行くみたい。手ですくい取れそうな赤。
会社の近くの駅から、五つ目の駅で降りる。寂れた小さな駅。ここから歩いて五分のところに私の住むアパートがある。歩きながら手をこすった。外は寒い。暮れも近いから当たり前だけど。
今日は十二月二十一日。
もう少しでクリスマスだから、道の途中の戸建の家ではイルミネーションが光っている。
二十一日かぁ……。あれ? なんだっけ。この日に何故か覚えがある。
そうだ。達也の手帳。
達也が日々の予定を書き込む手帳を、偶然見てしまった。
私の部屋のベッドの横にある小さい机に手帳を乗せたまま、達也はお風呂に入っていた。十一月の小春日和で変に蒸し暑かったから、部屋の窓を開けていた。
確かに達也は私の恋人だけど、手帳や携帯など、プライバシーに関わるものは覗かないようにしている。でもあの時、強い風が吹いて手帳の12月の予定のページが開いてしまったのだ。
そこに書かれていたのはシンプルな図だった。
そう、それが女の子の手帳ならありがちなカタチ。
十二月二十一日。ハートマーク。
私は驚いた。
だって他の日付にはそんなマークは一切ない。私の誕生日ですら、「真雪(まゆき) 誕生日」 と黒のボールペンで書いてあるだけ。
私はドキドキして、そっと手帳を閉じた。二十一日なんて……私の知る限りなんの記念日でもない。付き合い始めたのは三年前の夏だし。
あの夏。
高校時代の友達に無理矢理誘われて出た合コン。私は人数合わせだった。参加予定だった女の子が熱を出してしまったから。
引っ込み思案で、二十四歳になるその年まで誰とも付き合ったことなどなかった。他の女の子達が一番人生を謳歌する時期に、たかが合コンで私はガチガチになっていた。
達也は五人の男性参加者の中で一番背が高く、寡黙な印象だった。最初はむすっとした感じで取っつきにくかった。
「結構イイじゃん」と女の子達は囁きあってたけど、雰囲気が怖そうなので誰も話しかけたりしなかった。
席替えがあって、達也が私の隣に来た。私は人見知りだけど、一対一になると何か喋らなければいけない、という変な使命感に襲われるタチだ。
偶然外で遠雷が響いた。「雷って好きですか?」 と、おかしな質問を達也に投げかけた。
「……いや。特に」
硬い答え。まぁ、質問が質問だから言いようがなかったのかもしれないけど。
「私、大っきらいです」
そう言うと、達也は軽く笑った。
「女の人はみんなそう言うよね」
それは雷がなるとキャーキャー言って怖がることで、可愛さをアピールする女性への侮蔑の言葉のように聞こえた。
「うん。嫌いな人、多いですよね。大きな音も怖いし。でも私が嫌なのは、あの狙い撃ちってとこなんです」
達也はちょっと意外そうな顔で私を見た。
「だって、雷って人に落ちる時、大体一人を狙って落ちますよね。他の天災と違って、たくさんの人を巻き込まない。なんとなく、神様から特別に選ばれてしまった気がして、すごく怖いんです」
「天罰がくだる、みたいな?」
達也は面白そうに返事を返してくれた。こんなバカな話題についてきてくれるのが、私には不思議だったけど。
「うーん……と。実際雷の被害で亡くなられた方に、天罰が下ったとは思いません。でも、こんなにたくさん人はいるのに、なんで雷は一人だけ狙い撃ちにするの? って思う。せめてもっと仲間がいれば気も休まると思うのに」
言いながら、脇の下に汗をかいた。人が死ぬ話なのに、私の意見は突飛すぎる。
もっとたくさん死ねばいいと思ってるように聞こえてしまうかな。ひどい女だと思われたら嫌だな。でもいいか、今日限りの相手だし……。
私は言葉をそれ以上、続けることが出来なかった。目の前のカルアミルクを手に取って口に付ける。この店のカクテルは味が薄い。
「神様から選ばれた……か」
達也はつぶやくと、突然カクテルの乗っていたコースターをひっくり返した。店のご意見記入用に、テーブルに置いてあるマジックペンを取る。コースターの裏側にサラサラと数字を書いていく。
「これ、俺の携帯番号」
ポカン、と私は達也を見た。受け取るのを躊躇っていると、ぐいっと手の中にコースターがねじ込まれる。
「このお店はここまででーす。二次会に出る人は追加料金お願いします」
幹事さんの明るい声が座席に響いた。何と答えていいか分からないうちに、みんなが席を立ったので一緒に外に出た。
キョロキョロと周りを見渡す。達也が幹事の男性に手を挙げて、一人で去っていくのが目に入った。
私も二次会には参加せず、そのままアパートに戻った。部屋に入って窓を開け、扇風機をつける。床のクッションを引き寄せて、寄りかかって座った。
バッグを開けて、なくさないように大切にしまったコースターを取り出す。じっと番号を見つめた。せめてメアドならもっと気楽に連絡出来るのに。
私、電話なんかかけられる? もしかしたら、嘘の番号とか……。たまたま隣に座った変な女を巻くための、ひとつの手段だったのかも。
まるまる一週間、迷った。このまま忘れてしまおうかな……とも思ったけど、仕事をしていても、お風呂に入っていても、テレビを見ていても、コースターの数字が気になって仕方がない。
今では暗記してしまった番号。金曜日の午後七時。自分の部屋で正座して携帯を取り出した。
番号を押す。指は震えるし、心臓は口から音が聞こえてきそうなほど早く鳴っている。
プルルルル……。
発信音が聞こえる。
どうやら繋がらない電話番号じゃないみたい。
「はい。春川です」
会社での電話応対は別にして、父以外の男性の声が耳元で聞こえるのは初めてだった。緊張のあまり息が詰まる。最初の言葉がなかなか言えない。
「……もしかして、長瀬さん?」
私の名字を達也が言った時は、早鐘を打っていた心臓がそのまま口から出そうになった。
「あの……、そうです。名前、覚えていてくれたんですね」
「ああいや、実は分からなくて幹事から君の友達をたどって確認してもらったんだ。あんまり連絡がないから諦めようと思ったんだけど、やっぱりもう一度会ってみたくて。俺の番号を教えるんじゃなくて、長瀬さんの方を教えてもらえば良かった」
合コンで話した時より、はるかに饒舌に達也は喋った。私は達也の言葉に、力が抜けた。その日は次に会う約束だけして、電話を切った。
それからは、何もかもトントン拍子に上手くいった。会う約束をして、またもう一度会う約束をして……正式に付き合うことになった。
初めて手をつないで歩いた時、私が思い切って電話をかけた日は達也も私の番号を押そうとしていたと教えてくれた。
幹事のつてで聞き出した私の携帯番号。勝手に個人情報を教えないでよ、と思ったけど、この時は嬉しくて泣いてしまった。
それからもゆっくりとお付き合いして、お互いを知っていった。達也は小さな建設会社に務める設計士だった。ひとつ年上で地方から出てきて一人暮らし。
今まで数人、お付き合いした女性はいたみたいけど、どれもいつの間にか別れていたと言っていた。最後の人と連絡を取らなくなってから一年半が経過した、と聞いた。
俺が無口でつまんないからだろ、と達也は言った。私は自分もおしゃべりじゃないので、達也といると二人でボーッとしていることが多い。でもそういう時間が、まるで苦痛に感じない人だった。
ある日達也の部屋に遊びに行って、借りてきたビデオを観た。画面がエンディングを流したとき、肩を抱き寄せられ、唇が重ねられた。それまでも何度かキスしてきたけど、この時は多分、それ以上の事が起こると覚悟していた。
私にちゃんと出来るかな……。不安ばかりが頭につのる。いつものキスから、もっと深いキスへと変わっていく。達也の背中に回した自分の手が、期待と恐怖でブルブル震えるのが分かった。
達也はキスをやめると 「もしかして……初めて?」と聞いた。私は首だけ縦に振って肯定した。恥ずかしい。もし達也がバージンが嫌いだったらどうしよう。
「いいの? 俺で……」
低く、達也の声が問い返す。
私を抱く達也の手がギュッと固く握られる。それを体に感じて、達也も怖いのかもしれない、と思った。急にどうしようもなく達也が愛おしくなって、私は力を込めて達也を抱きしめた。
「好きなの。達也のこと、本当に好き」
手と同様に声も震える。
いい年して、バカみたい。
友達はみんなバージンを高校の時捨ててる。私は好奇心より、本当に好きな人と初めてを経験したかった。そのまま、ズルズルここまで来た。
運命の相手とか、激しく恋に落ちるとか、そんなんじゃない。でも達也のことが心から好きと思える。そう思えた、自分が愛おしい。
達也の息がどんどん乱れていく。いつもより、少し乱暴に持ち上げられる。ベッドまで運ばれて、全部服を脱がされる。体中にキスの雨が降る。最初硬かった私の身体が、段々潤いと柔らかさを増していく。
痛みと共に来たのは、喪失感ではなかった。まして、やっと捨てられた、という安堵感でもない。自分の中に深く押し入っている達也自身を感じる。
初めて「完成した」という気がした。奇妙な感想。
もっと快楽を味わいたいだろうに、達也は私を気遣って激しくは動かない。一回目はそのまま終わってしまった。達也がきちんと最後まで〝いけた〟のかどうか、ウブな私には判別がつかなかった。
達也はベッドの中で、私の体にそっと手を滑らせながら目を閉じていた。私は達也の腕の中から、ベッド脇の窓から見える空を眺めた。
四角い空はもうとうに暮れて星が光っている。今日は月が見えない。新月かな……とつぶやいた。
「今夜は……帰さなくて、いい?」
そのセリフには思わず吹き出しそうになった。なんだかトレンディドラマのワンシーンみたい。明日は休みだし、一人暮らしで誰にも迷惑はかけない。私は笑いを隠すために、達也の肩の下のくぼみに顔を押し付けた。
「いいよ……」と返事する。
一度目より二度目の方が余裕があるはず、と思ったのが間違いだった。今度の達也の攻めは、さっきの比ではなかったから。
しっかりと時間をかけて行われた優しい愛撫の後は、息もつけないほどの激しい攻撃だった。さっき一度貫かれたから、二度目は最初ほどの時間をかけずに埋め込まれた。
達也の動きは徐々に力強くなっていく。身体がずり上がってしまわないように、必死で達也の肩に掴まった。最後は達也の腰に自分の脚を絡めないといられなかった。自分がこんな格好をすることが現実に起こるとは思わなかった。でも恥ずかしさよりも、快感と愛しさの方が強かった。
今回は、達也が最後まで到達してくれたのが分かった。私にもちゃんと出来たんだ……と思えて嬉しかった。クタクタになって、達也の腕の中で眠った。
それから何度も続いた夜。
私と達也の愛の記憶。
駅からアパートまでの道を歩きながら、達也の手帳のハートマークを思い出していた。あれはなんだろう。
……多分……多分、達也は私に秘密はない。そう思いたい。でもあのマークの意味は分からない。
今日がその日なんだ。まさか誰か他の女性と会ってたりして。そうだったら私はどうするだろう。なんとなく、戦うこともせず身を引いてしまうかもしれない。
道端の草が枯れている。十二月なのだから当たり前だ。
でも通り道にある木々の葉や枝も、変にしなびている。そういえば、今年は空梅雨で秋の長雨もあまり続かなかった。お湿りがないので、十二月はずっと乾燥注意報が出ている。私のお肌もカサついている。もっとしっかり保湿クリームを塗らないと肌が割れそう。
アパートに着いた時、空には赤い夕日の筋が残っているだけだった。暗いはずの自分の部屋に明かりが灯っている。
私は急いで部屋の鍵を開けた。もしかして、実家から母が来たのかも。母は時々突然やってくるから困る。特にカレが出来てからは部屋に置くものにも、すごく気を遣う。
ガチャリ、とノブを回してドアを開ける。「おかえり」と低い声が響いた。
「え!? 達也……あれ、今日会う約束してたっけ?」
私は焦った。達也と会う約束を忘れたことなんて今まで一度もない。
「約束はしてないよ。約束しなきゃ、来ちゃいけない?」
少し不服そうに、でも笑いをにじませて達也は私を見た。私は首を振ると、靴を脱いで部屋に上がり、達也に飛びつく。
「嬉しい、会えて。明日の土曜日まで会えないと思ってたもん」
達也が耳元でフッと息を吐いて笑う。私を軽く離すと、頬に手を添え唇が押し付けられる。熱く甘いキスを交わしながら、達也の手は私のスカートの奥を探る。
達也の指が私の中に差し込まれる。思わず低く呻いてしまう。達也は楽しそうに 「準備はバッチリだね」 と言った。
私は真っ赤になった。最近は達也と二人になると身体が勝手に期待して潤ってくる。私は達也の手を押し返そうとしたけど、強い力で抵抗される。
腕の力は強いのに、指は柔らかく巧みに動く。自分の鼓動と、達也の指の動きのせいで起こる溢れる蜜の音が部屋中に鳴り響いてるような気がする。羞恥と興奮がない交ぜになる。
私も達也のベルトを外し、中に手を差し込んだ。そっちこそ、準備オーケーじゃないの?と言いたかったけど、より強く激しくなる愛撫に言葉なんか出てこない。
服を着たまま、一つになった。達也は私の名前を何度も呼ぶ。その呼び方がいつもと違う。切羽詰っていて追い詰められてる感じ。
私は少し不安になった。
終わってから、お腹の上をティッシュで拭いた。達也はまだ軽く息を弾ませながら、私の行動を見ていた。
「……ね。すごくいい匂いがするけど、もしかして晩御飯作ってくれた?」
私は達也の視線がなんとなく怖くて、気楽な会話をしてみようと話しかけた。達也は曖昧に笑うと、「今頃気づいたか」と言って立ち上がる。履いていたジーンズを直すと、狭い台所に向かった。
「夕飯は出来てるよ。ホワイトシチューに鶏肉のステーキ。冬の定番。CMみたいだろ?」
「やった。嬉しい、大好物。手を洗ってくるね」
私も服を整えて立ち上がった。台所に立つ達也の後ろ姿が、何だかいつもより小さく見えた。また強い不安が襲ってきて、私はふざけて明るく言った。
「そういえば、手洗いうがいもしないでキスしちゃった。インフルエンザにかかってたら、達也にも移るかもしれないよ」
電車の中はマスクをつけている人が沢山いた。インフルエンザも例年通りに流行り始めた。空気が乾燥しているから、感染率は高いはずだ。
「構わないよ。移ったって、もう発症することもないだろう」
その言葉は、遠くから聞こえた。私は話しながら洗面台に移動していたから。しっかりうがい手洗いをしてから、達也のところに戻った。
ドキドキする。いつもと違う気がする達也の行動と言動。息が苦しくなってきた。
テーブルには白いカバーが掛けられ、暖かい食事が並べられていく。手伝おうとしたけど、達也は「座っててくれ」と言って全部用意してくれた。
食事は美味しかった。達也はそれほど料理はしないと言っていたけど、私より上手いかも。
後片付けは強引にやらせてもらった。全部やってもらうなんて、申し訳ない。私が片付けている間、達也はずっと窓の外を見ていた。今日はテレビもつけない。また胸が不安でいっぱいになる。
食器を棚にしまってから、達也の隣に立った。「……始まったな」と達也が囁く。
何が? と聞こうとして、息がますます苦しくなるのが分かった。さっきから、達也への不安のせいで息苦しいと思っていた。でも今は本当に苦しい。
達也は私を見た。達也の息も途切れがちだ。やはり同じように苦しいのだろうか。
私は達也を見上げた。達也は哀しそうに私を見る。その目から涙がこぼれた。
「……俺は、真雪に会えて良かった。真雪と出会えて、愛し合えたことが俺の人生で最高の幸せだ。本当は結婚したかった。真雪に、綺麗なウエディングドレスを着せてやりたかったのに……ごめんな」
「なんで謝るの? どういうこと?」
私は意味が分からなくて、達也に問いかけた。息が苦しい。こんなのは一度も感じたことがない。
「世界の終わりだよ。何かの予言であったんだ。十二月二十一日、この世界は終わる。まさか本当だとは思わなかった。でも周りの植物を見て、俺は確信できた。誰か──大学の教授かなんかが言ってた。
この世界が終わるのは、全世界の植物が一気に枯れる時だって。人間は好き勝手やりすぎた。地球温暖化は止められない。生物は植物に復讐される。もう、植物は酸素を供給してくれない。枯れてしまうんだ。全部。それが始まってる」
私の身体が硬直した。それでは……今日?
今日、この日に世界が終わるの?
私も、達也も、死んでしまうの?
達也は不意に私を抱きしめる。服を脱がされていく。
「今日は……絶対、真雪に……会いたかった。何が、起こ……ても絶対会お……と決めてた」
達也の声が途切れるのは、私と深くつながって喘いでいるからだけじゃない。私も残り少ない酸素を吸い込もうと、息遣いが荒くなっていく。
いつも聞こえる車の音や電車の音が全くなくなる。
それは静かにやってくる。
世界の終わりは静寂に包まれている。
達也の背中を抱き寄せながら、私は絶頂の悲鳴を上げる。私も、あなたに会えて良かった。そう言いたかったけど、今はもう、達也の名前を繰り返すことしか出来ない。
最後の息を吸い込んだ瞬間、愛しい達也の声が聞こえた。
「愛してるよ……ずっと……」
2012.12.15 FLS掲載作品